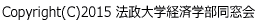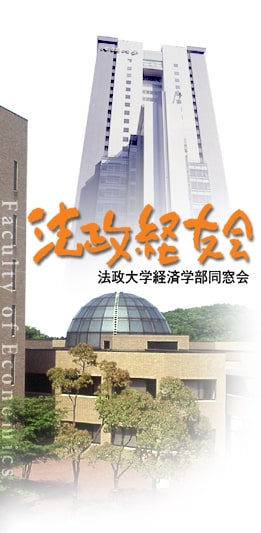
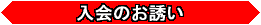

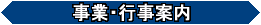
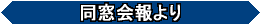
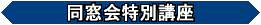

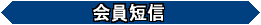
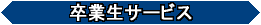
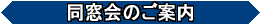
![[同窓会からのお知らせ]同窓会からのさまざまなお知らせはここから](../m_info.gif)
![[リンク集]同窓会や法政大学関係のリンク集](../m_link.gif)
![[創立25周年記念事業]特設サイトへ](../25thspecial.png)
法政大学経済学部同窓会は
創立25周年を迎えました
![[卒サラ・起業家インタビュー・シリーズ]へ](../sotsusara.jpg)
法政大学経済学部同窓会事務局
〒194-0298
東京都町田市相原町4342
電話・FAX:042-783-2550
(火・水・金曜 9時〜16時)

| 第 22 回 (2014年) 受 賞 者 |
|---|
| A賞 | 川上 忠雄『1847年恐慌』(御茶ノ水書房,2013年) |
|---|
■第22回森嘉兵衛賞について
森嘉兵衛賞審査委員会は、慎重に審査した結果、本年度の森嘉兵衛賞についてA賞として川上忠雄『1847年恐慌』(御茶ノ水書房、2013年、5,600円)を決定した。
川上忠雄氏は、講評にもあるように、東大経済学部修士課程修了後、本学に助手として採用され以来本学の専任教員とし教育、研究に励み、時には大学行政に大きく関わってこられた。2003年に本学を定年退職して後、10年後に本書を上梓されたその学問的な情熱は特筆すべきものがある。
この度、森嘉兵衛賞に推薦された『1847年恐慌』は、若き頃研究課題にされ、研究半ばにされていたものを、40数年後に完成されたものである。氏のこれまでの恐慌論の総仕上げである。審査委員会は、川上忠雄『1847年恐慌』は、講評にあるように、森嘉兵衛賞A賞に値する優れた著作であるとして決定した。
2014年3月末日
森嘉兵衛賞審査委員会
委員長:経済学部長 牧野文夫(経済学部教授)
委員:主査・粕谷信次(法政大学名誉教授)、廣川みどり(経済学部教授)、
武田浩一(経済学部教授)、村串仁三郎(法政大学名誉教授)
■著者略歴
 川上 忠雄(かわかみ・ただお)
川上 忠雄(かわかみ・ただお)1933年 徳島小松島に生まれる。
1956年3月 東京大学経済学1959年3月部卒業。
1959年3月 東京大学大学院修士課程修了、修士となる。
1959年4月 法政大学経済学部助手となる。
1962年3月 法政大学大学院博士課程単位取得。
1962年4月 法政大学経済学部専任講師。
1965年4月 法政大学経済学部助教授。
1971年4月 法政大学経済学部教授。
1993年5月〜99年4月 常務理事。
2003年3月 法政大学を退職、名誉教授となる。
主な著書
1971年 『世界市場と恐慌』(上巻)、法政大学出版局。
1973年 『第二次世界大戦論』、風媒社。
1975年 『労働者管理と社会主義』、『工場闘争と労働者管理』(共に佐藤浩一との共著)、共に、五月社。
2003年 『アメリカのバブル1995-2000』、法政大学出版局。
 ■講評
■講評著者は、「1847年恐慌研究は、ほとんど生涯の研究テーマであった」と述懐する(『1847年恐慌』まえがき)。まさに文字通り、恐慌史をテーマにして始めて研究の成果(1962年以来、10回に分けて『経済志林』に連載)を、まず1971年、第一部 自由主義時代の世界市場(『世界市場と恐慌』上巻)として上梓した。その際、動態分析の典型として、「1847年恐慌」が第二部として、編、章、節、項に至るまで詳細に紹介され、近刊が予告されていた。しかし、研究が中断され、それは刊行されなかった。
40年余の中断の後、昨年(2013年)『1847年恐慌』がようやく日の目を見た。それをどう考えるか。一見したところ、編、章、節、などが同じで、大きな違いはないように見える。また、著者の研究に対する高い評価は、『経済志林』発表論文、そして『世界市場と恐慌』上巻(1971年)によって既に定まっている。自ら指摘するように、歴史は歿理論的な事実の積み重ねではなく、具体的事象の時空の有機的関連の全体的、統一的認識こそが理論であるという。そうであるからここ、二つの理論問題、恐慌の直接的契機を最好況期末の金流出に求めること、生産方法の改善が不況期に集中する事実を突きとめることを通して、恐慌史研究と恐慌理論研究に大きく貢献したことは、すでに定評のあるところである。今更評者が蝶々するまでもない。評者には、著者の40余年の中断が何を意味するのかを考えることの方が今は興味深い。
決定的なことは、資本主義下の人間と社会の問題性認識に突き動かされて、「真のマルクスを追い求め」(『1847年恐慌』P.ii)、自信をもって、革命的実践運動に飛び込み、再起不可能なほどの挫折の奈落に投げ込まれてしまったことであろう。
そうなった時、多くの場合、全く冷笑的になるか、転向して真逆に走り出すか、全くの無関心に陥る。しかし著者は、長い、長い思想的苦闘を、時に真正面から時に大きく距離を置いて、続けていたのである。そして40余年後の今日、次のようにいうのである。「私自身根本からの思想的問い直しを必要と感じている。何より唯物史観の宿命的な歴史の必然性論、そしてそれと一体の人類は進歩するとの歴史観をきっぱり捨て去らなくてはならない。これらは人々の心を縛りつけ、目を見えなくさせてきた。呪縛から自由になって虚心に現実を見なければならない。」(『1847年恐慌』P.iii)
そして見えてきたのは、自然との共生の中でしか持続可能でない人間社会のカタストロフィーへ向かっての暴走(かつて救済に乗り出した国家システムも今や再編能力を失い)であり、この道に抗する方途は、広く、深く、社会哲学、人間哲学の深みからの見直しを必要とすると論じる。
今回上梓された『1847年恐慌』は、そのような広さ、深さをその背景にもって再論されているのである。恐慌史、恐慌論、経済学に限らず、社会科学の有り様に一石も二石も投ずるものをもっていると思う。(法政大学名誉教授・粕谷信次)